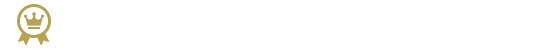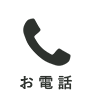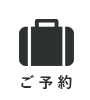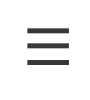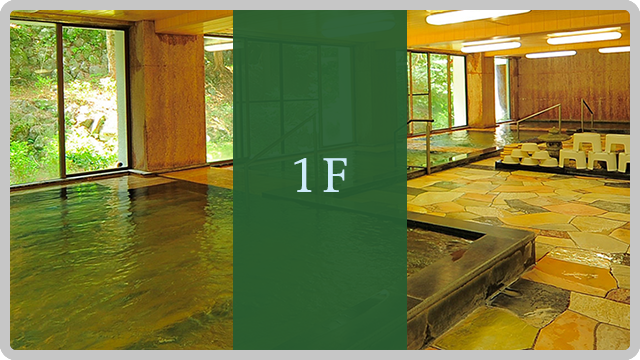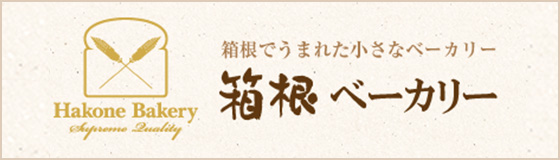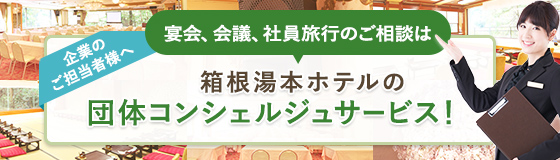杉並木
箱根には多くの杉並木が残っています。この並木の起源は遠く奈良時代までさかのぼります。天平宝治3年(759)に、東大寺の僧普照の奏上によって、駅路の両側に果樹を植えたのが並木の始まりといわれています。
江戸幕府もまた街道に並木を植えることを命じています。記録によれば、徳川家康が江戸幕府を開いた翌年の慶長9年(1604)に、東海道をはじめとする諸国の街道の両側に松や杉を植えたというのがそれです。 並木は、暑い夏には旅人に緑陰を与え、冬は吹き付ける風や雪から旅人を守ります。また風雨や日差しから道そのものを守る役割もありました。
柳田国男によると、並木は路標の役割をも果たしたといいます。雪で道がわからなくなったときに、並木に沿って歩けば迷うことがないからです。
ところで、神奈川県内の東海道を通してみると、川崎宿から箱根宿までの約60%の区間に並木が存在していたことがわかっています。その種類も海沿いの道には松を、そして箱根では杉というように、その土地の自然環境に適した樹木が選ばれています。
現在も、有名な箱根の杉並木をはじめ、藤沢、茅ヶ崎、大磯などに松並木が残っています。
箱根の杉並木も例外ではありませんでした。明治の中学唱歌『箱根八里』に「昼なお暗き杉の並木…」と歌われた箱根の杉並木は、箱根ばかりか、東海道を代表する風景といっていいでしょう。
箱根町教育委員会が、今までに枯れて伐採された杉の年輪を調べたところ、樹齢は最高でも350年ということです。ですから十年生の苗木を植えたとすると、340年前、つまり1660年ごろに植えられたということになります。
現在、箱根には芦ノ湖畔を中心に412本の杉並木が残っています。しかしかつてはもっとたくさんの杉並木がありました。というのも明治37年(1904)に、湯本から芦ノ湖畔に至る新道を工事するときに、工事費が不足したため、並木を伐採売却して工事費の足しにしたことがあり、この時点で切り倒された並木は、松と杉を合わせて、1024本に及んだというのです。
箱根町教育委員会の調べによれば、現存する杉のうち、良好な健康状態を保っている木は412本のうちわずか30%。100年後には現在の三分の一の本数になってしまうかもしれないとさえ危惧されており、箱根町教育委員会では見事な杉並木を未来に伝えるため、その保護活動に力を注いでいます。
宿場
東海道は、江戸・日本橋から京・三条大橋に至る道です。その距離約492kmにもなります。途中、武蔵、相模、伊豆、駿河、遠江、三河、尾張、伊勢、伊賀、近江、山城の国々を通り、53の宿場がありました。
神奈川県内には、そのうち川崎宿、神奈川宿、保土ヶ谷宿、戸塚宿、藤沢宿、平塚宿、大磯宿、小田原宿、箱根宿の9つの宿場がありました。川崎宿から箱根宿までの距離は約80km。その最大の魅力はなんといっても、街道沿いに展開する変化に富んだ風景です。
江戸を出発すると、まず左手に江戸内湾を眺めながら川崎、神奈川と進み、保土ヶ谷、戸塚、藤沢では三浦半島によって海は一時視界から消えますが、やがて平塚、大磯では相模湾が現れ、酒匂川を横切ると、小田原からは箱根山中の上となり、難所ですが山上には芦ノ湖が、そして眼前には富士山が聳えるといった具合です。
小田原宿が成立したのは慶長6年(1601)です。かつて関八州を統一した後北条氏の城下町として繁栄した小田原は、関東の出入り口として重要な拠点でした。
小田原は宿場町としての機能を備えた城下町であり、町の形成も領主の居城を中心に整備され、宿場町としての特有な町割(まちわり)となっていました。その規模は神奈川県内では最大の宿場町といってもいいでしょう。
本陣と脇本陣が4軒ずつあり、これは東海道53宿の中では最も多く、庶民の利用した旅籠屋も江戸後期の天保年間には100軒を超えるにぎわいを見せていました。
町人町には土産屋、食事屋、雑貨屋、衣料屋、魚屋などを生業とする商人の家が建ち並び、城下は活気に満ちていました。今でも名物として有名な蒲鉾や梅干し、小田原提灯などは、江戸時代から続いているものです。
一方で箱根宿の成立年代は確定されていませんが、『新編相模国風土記稿』によれば、元和4年(1618)に、箱根山越えの便宜を図るために宿場を新設したと記されています。
さらにその場所については、土俗の伝えとして、幕府は初め、古くから箱根権現の門前町として栄えた元箱根を宿場としようとしましたが、それができなかったため、芦ノ湖畔の原野で人気のない今の箱根町箱根に宿場を設置したといわれています。
このとき、隣宿の小田原宿と三島宿からそれぞれ50軒ずつ移住させ、宿場を設けたのです。現在の箱根町箱根には、字として小田原町、三島町という名前が残っていますが、この字名はこのときに由来するものと伝えられています。
ところでこの字名は、たんなる表記という意味ばかりでなく、小田原町は小田原藩領分であり、三島町は三島代官所(宝暦期以降は韮山代官所)が管轄する天領であるという意味を持っていました。つまり江戸時代を通じて箱根宿は、1つの宿場でありながら、2人の領主を持つという特殊な宿場だったのです。このような支配形態を持つ宿場は、東海道五十三次の中で箱根宿だけです。
わらじ姿の旅人たち
江戸時代の旅人は一般的に江戸を立って京に向かう場合、最初の宿泊地となったのが戸塚宿、あるいはその手前の保土ヶ谷宿でした。
日本橋から保土ヶ谷宿までが八里九町(約33km)、戸塚宿までは十里半(約42km)です。つまり昔の旅人の1日の行程はおよそ八里から十里強(約32~40km)と歩いたといわれています。もちろんこれは成人男子の場合ですが、歩行速度を時速4kmとすると、単純計算で約8~10時間も歩くことになります。そのためには夜明け前に出発し、夕方日が暮れないうちに次の宿に着くようにしていました。
この計算から日本橋から京までは一般的に、徒歩で13日から15日前後かかっていたようです。 江戸日本橋から京都三条大橋までの距離は約492km。15日とすると、1日平均約33kmも歩く計算になります。
『東海道中膝栗毛』の弥次郎兵衛・喜多八(弥次さん喜多さん)の二人が江戸を出て最初に泊まったのは戸塚宿ですが、2日目は戸塚から小田原まで約40km、3日目は小田原から箱根まで約30km強を歩いています。
2人はこのペースで江戸から四日市まで12日かかっています。このあと東海道を離れ伊勢参りをしたあと奈良を回って京に出るわけですから驚愕というほかありません。
毎日10時間も歩きつづけながら目的に向かうというのは、現代では考えられそうもありませんが、履物も草鞋履きであったことも考え合わせると、一般的に昔の人は想像以上に健脚だといえそうです。
「天下の剣 箱根山」の箱根越え
箱根は東海道で最大の難所として古くから恐れられていたところです。藤原為家の側室阿仏尼は『十六夜日記』(いざよいにっき)で箱根路のことを「いとさかしき(大変険しい)山をくだる、人の足もとまりがたし、湯坂とぞいうなる」と記しています。
つまり旅人がどのように箱根山を越えるか、悩んでしまうくらいそれほど過酷であったことが伺われます。
鎌倉時代には、箱根山を越える道には、京から下る場合、三島から御殿場を迂回して足柄峠を越え、関本から国府津へ抜けるいわゆる「足柄道」と、直接箱根山を登り、芦ノ湖を経て箱根権現を通り、湯本へ下るいわゆる「湯坂道」と呼ばれる2つのルートがありました。
江戸時代になると、徳川家康が街道整備に着手する中で、箱根山越えの道は大きく変更されます。いわゆる「箱根八里」とよばれるルートです。この道筋は、江戸から京に向かう場合、湯本の三枚橋で早川を渡り、須雲川沿いを登り、畑宿を経て芦ノ湖畔に出る道です。途中、険しい坂道が続き、山道には茶屋が13カ所もありました。
この大自然につつまれた箱根湯本ホテルは、大地の恵みを存分に受けていることはもちろん、重要な歴史に登場する史跡にも恵まれた由緒ある土地に位置しています。歴史に登場する江戸時代の史跡が当館に存在しているわけです。
箱根の自然と調和をしながら歴史を訪ねる・・・・・。
わたくしたち箱根湯本ホテルはこんな楽しみ方も提案しながら、お客様をお迎えしています。
箱根を五感で楽しむゆえんです。箱根湯本ホテルならではの「あなただけの箱根」にご案内いたします。